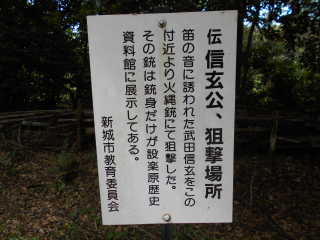大乗寺山門と城跡の石碑

本多忠高の墓
室町時代中期に築城されたといわれる。
1471年 松平家(のち徳川家)3代・信光が攻めとり、以後、4代にわたって松平家が支配する。
1524年 松平家7代・清康が岡崎城を攻めとり、本拠を岡崎に移す。
1535年 守山崩れ。清康が殺害され、広忠が跡を継ぐが、松平家が弱体化する。
1540年 第一次安城合戦。尾張の織田信秀により落城(安祥城落城年は諸説あり)。
1545年 第二次安城合戦。織田信秀、攻め寄せた松平広忠を撃退する。
1549年 第三次安城合戦。城将・織田信広、今川義元の軍師・太源雪斎を撃退する。
第四次安城合戦。雪斎により落城。城将・織田信広が捕虜となる。
1562年 清州同盟。織田家と徳川家が同盟したことにより、前線拠点の価値がなくなり廃城。
(メモ)
現在、本丸跡は大乗寺、曲輪跡は八幡社となっているが、縄張り図と比べてみると地形がけっこう残っていることが分かる。
第二次安城合戦のときに本多忠豊(忠勝の祖父)、第三次安城合戦のときには本多忠高(忠勝の父)が討死しており、大乗寺の墓地には岡崎藩主となった子孫が建てた忠高のお墓がある。
1547年、松平広忠は嫡男・竹千代(のちの家康)を人質として今川義元のもとへ送ろうとしたが、織田信秀に強奪されており、広忠の死後、太源雪斎が捕らえた織田信広との人質交換で竹千代は帰還した。その後、改めて義元のもとへ人質として送られている。
時間があれば、安城市のソウルフード「北京飯」をお試しあれ。


 堀跡(清海堀)
堀跡(清海堀) 東照公(家康)産湯井
東照公(家康)産湯井